これは今年の1月6日。
雪の中、夕方から出かけなければならなくなり、
歩いて行った途中、学校近くの竹町公園。
こちらは今日。
枝に雪を積もらせていたのは桜だったのだと、
桜の花を咲かせた枝を見て。
春は4月、何かが始まる季節。
でもその前の3月は、何かが終わる季節。
これにて現役引退の友だち、知り合いもいて、
なんとも言えぬ思いを伴う今年の春、桜です。
みんなの次のステージに、乾杯(^.^)/□
口惜しいは、残念とか、くやしいとかいう意味です。
『枕草子』では、
準備を整えて待っていたことが、いきなり中止になってしまうこと、
遣いまで出したのに、招いた人が来ないこと等々、いと口惜し。
私版では、
とうもろこしが物凄く好きなんですが、それを焼きながら
喋っていたら黒こげになってしまったのはとても残念。
注文したサラダに、全体を覆うように薄切りのきゅうりが
かぶさって出てきたのは残念すぎ。
(一昨日書いたように私はきゅうりが苦手なので。)
いと口惜しのこと、あまたあるけれど、
それを上回る、嬉しきこと、楽しきこともあまたあるので、
行って帰ってで、まあ、よしとしましょうですね。
写真は、私のフォルダ検索したら出てきた、
世界あちこちで食べたとうもろこし。
食べ物の中で、きゅうりが唯一苦手です。
そのきゅうりが今よりずっと青臭かった高校時代、
鼻で臭いを感じないように、口だけで息をしながら、
きゅうりの薄切りの練習をしました。
普通科と家政科がある女子校の普通科だったんですが、
家庭科検定?を受けるのは普通科の生徒も必須でした。
どうしてこの話題を思いついたかというと、今朝の日経、
「4月1日 高校で新指導要領が始動」という記事を読んで。
IT・投資、実学的学びが拡充されるそうです。
ITは知っていたけど、投資も?? いいな今の高校生。
自分の10代のころは、中学から男女別々の科目ができて、
男子は柔道、木工、女子はダンス、調理実習、といった具合。
柔道やりたい、木工やりたいと、先生に言いに行ったけれど、
認められず。そんなことを単独でしてたのでしたよ。
思い出すと、良妻賢母育成を目指していたのかなと思うような
高校(地方なので選択肢が少ない)での家庭科検定でした。
が、そんな中、倫理社会の課題で書かされた!?作文、
「主婦について」だったか、そんな内容に対する自分の意見。
考えに考えて、主婦は報酬はないけれど立派な仕事、みたいな
ことを書いた私の文に、課題を出した女性の先生は、赤ペンで、
経済的基盤のない自立はあり得ません。
それが今の自分に繋がっているのかどうかはわかりません。
が、事あるごとに思い出す、このO先生の文字です。
その女子校は今年の春、男子校と統合されて校名が変わります。
私の後、何年ごろまで、きゅうりを切る家庭科検定の受験が
必須だったのかは知りません。
写真は今。近未来の!?日本語教育を話し合う次世代の人たち。
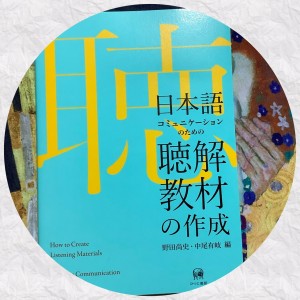
『日本語コミュニケーションのための聴解教材の作成』
野田尚史・中尾有岐 編 ひつじ書房
郵送された包みの表に「著者献本」とありました。
文化審議会国語分科会日本語教育小委員会や、
日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議で
ご一緒させていただいた野田先生より。ありがとうございます。
日本語コミュニケーションのための聴解教材作成の基本方針は、
「日本語学習者が実際に聞く必要がある日本語や聞きたいと思う
日本語聞いて、その意味を理解できるようにするための教材」
と、最初の章にありました。
聞く必要がある日本語、聞きたいと思う日本語。
それが学ぶ必然、モチベーションの大元。聞くことに限らず、
それが基本だと教えられ、ずっとそう思ってきたけれど、
決められたカリキュラムやテキスト“で”教える場面では、
なかなか難しいという状況(言い訳?)の下、それができず、
結果的に、本当に力をつけられているのかなと思うことが、
先生たち、きっとあるんじゃないかと思います。
日本語学習者の多様化が進んで、今までよりもっと、
それぞれに合わせた日本語教育の提供が必要になってきています。
「「文型」から出発して教材を作成するのではなく、日本語に
ついての調査や学習者を対象にした調査をもとに教材を作成すること
を方針にしている」ともありました。
これは、教材だけでなく、学校も同じことですよね(肝に銘じる)。
私はインターカルト日本語学校は小さな地球だと思っています。
それは、ここに世界中の違う文化やことばがあるからです。
皆さんはここで、日本や日本語だけでなく、
地球上のたくさんの国と、ここに集まった一人一人の友達の、
様々な考え方や価値観に触れることができます。
と、こんな話をいつも入学式でします。
今年の春は、いつも以上の思いを持った、いつも以上の数の
新入生たちがやってきます。
私たちもまた特別の思いを持って受け入れ準備をしています。
このように、「いつも以上の」「特別の」なのだけれど、
でも、いつもと同じなのは、世界中の様々な国から学生たちが
来ること。もちろん日々ニュースで報道されている国々からも。
私たちの小さな地球が受け入れているのは、
「国」ではなく、一人一人の「人」です。この環境だからこその、
ことば以上のことを、学生たちには学んでほしいと思っています。
「さいた さいた チューリップのはなが〜♪」
ですが、口をついて出てきた、
「サイタ サイタ サクラ ガ サイタ」
戦前の小学校の国語の教科書です。
戦後の私の小学校一年生のときの教科書の最初は、
「みえる みえる」
次は、
「はるみさん はい」
その次は、
「おおきいな おおきいな」
でした。
ついさっきのことも忘れるのに、どうして覚えているんでしょ。
人の脳みそには、記憶の引きだしというのがあって、
年齢と共にそれが一杯になり、そうすると新しい情報は溢れて、
どこにどうあるかがわからなくなる。つまり、思い出せない。
でも古いことは結構整然としまわれているから、すぐに出てくる。
(私の説。)
ついでに、中学の英語の教科書の登場人物は、
ヴィンセント、スタニスラス、グロリアでした。確か、三省堂の。
いわゆる英語の教科書の…じゃない名前が気に入っていました。
明日(もう今日)締め切りのものが終わらなくて、
飲んで帰ったのではないのに午前様。
時間を少し戻して、24日の文、以上です。ふう。
卒業生たちはそれぞれのクラスの教室にいて、
卒業証書は代表者に私が渡し、他の皆は教室で先生から。
そして、皆勤賞、精勤賞、インターカルト賞の学生たちが、
代わる代わる、私たちがいる1階のラウンジに来て、
賞状を受け取って、また教室に戻って行きました。
コロナのための特別措置でビザが延長され、
3年間在籍した学生の中の3人が精勤賞を受賞しました。
1年半在籍で皆勤賞だった学生より、実はすごかった出席率。
日本のインターカルトに一日も来ずに、最初から最後まで、
オンラインで国から授業を受け、そのまま進学が決まった
学生も何人かいて、彼らも卒業式に参加してくれていました。
卒業生一人一人のスピーチで、学校への感謝の言葉を言って
くれて…涙涙です。
マレーシアとタイと台湾の事務所の皆さんもオンラインで参加、
台湾の孫さんが画面の向こうで撮ってくれた写真です。
このコロナ下、留学を続けてくれたすべての学生たちへの思いは、
感謝以外の何者でもありません。